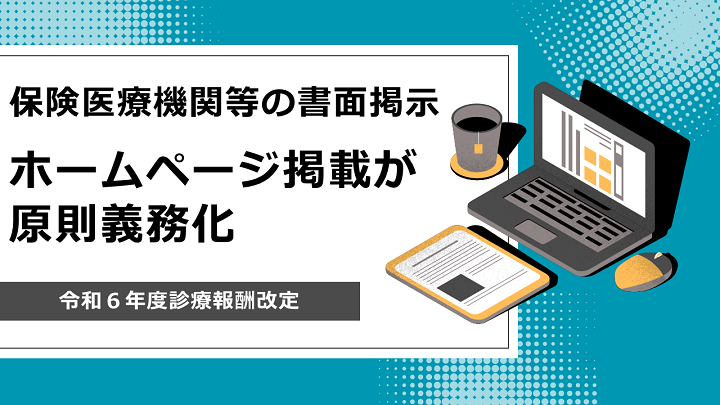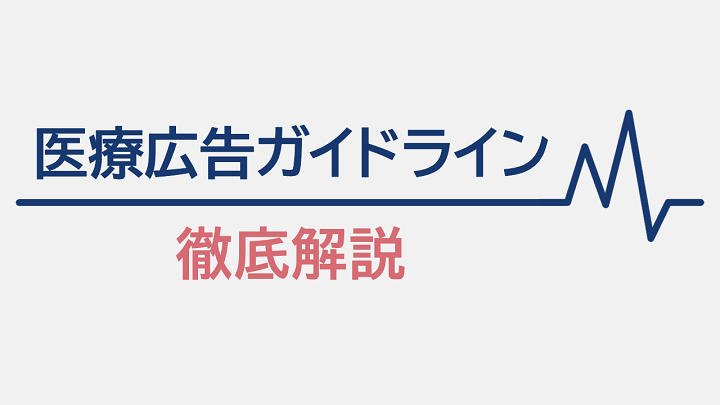クリニック経営における「集患」の重要性
医療業界の競争が激化する中、クリニック経営において「集患」は避けては通れない課題です。特に少子高齢化や人口減少が進む地域では、患者数の確保がますます難しくなっています。患者数が減少すると、収益の減少だけでなく、スタッフのモチベーション低下や雇用の削減による診療の質の低下につながる可能性もあります。一方で、安定した患者数を確保できれば、経営基盤が強化され、医療の質を向上させるための設備導入やサービス改善、人材確保への投資が可能になります。つまり、「集患」はクリニックの経営を支える柱と言っても過言ではありません。このコラムでは、クリニックが抱える集患の課題と、その解決策について詳しく解説していきます。
クリニックが集患できない原因は?
「思うように患者が集まらない…」そんな悩みを抱えるクリニックは少なくありません。
まずは患者が増えない理由を考えてみましょう。
理由その1:認知度の低さ
開業してしばらく経つと、地域内での新規患者の流入が鈍化することがあります。これには、地元住民がすでに他の医療機関を利用していることや、クリニック自体の存在が広く知られていないことが影響しています。特に住民の出入りが多い地域では、自院の認知度を上げるための対策が求められます。
理由その2:競合の増加
近年、多くのクリニックが開業し、患者が選べる医療機関が増えています。「歯医者はコンビニの数より多い」と言われるとおり、歯科では66,000以上のクリニックが開業しています。医科でも、たとえば内科を届出しているクリニック(内科、一般内科、総合内科など)は50,000以上あり、自院の特徴や強みが明確でないと、数多のクリニックの中に埋もれてしまう可能性が高くなります。
理由その3:情報発信不足
医療機関を受診するとき、患者の多くは事前にインターネットで検索して、診療内容や設備、アクセス方法などの情報をもとにクリニックを選んでいます。ホームページなどの広告媒体を活用していない、または発信している情報が不十分だと、患者がクリニックを選ぶ際の選択肢から外れてしまうかもしれません。集患を目指すうえで、「情報の発信」も課題のひとつです。
集患対策の具体例
集患を成功させるための対策は、「オンライン対策」と「オフライン対策」の2つに大別されます。
オンライン対策
オンライン対策とは、インターネット上で行う集患対策です。
オンライン対策の中心はホームページ
今では多くの患者がインターネットを利用してクリニックを探すため、集患のためにはホームページの制作は必須といえるでしょう。ホームページをすでに持っていても、作成後に放置していてはいけません。ホームページ上の情報は常に最新・正確な状態を保ちましょう。
ホームページはわかりやすいデザインと使いやすさが大事
 患者がホームページに訪れた際、求めている情報に素早くたどり着けるかどうかは、ホームページを制作するうえで大切な視点です。たとえば、診療時間や診療科目、クリニックの所在地などの基本的な情報は、トップページや目立つ位置に配置する必要があります。こうした情報が見つけやすいだけで、患者の安心感や信頼感が格段に向上します。また、ホームページ内の各ページにメニューボタンなどを設けることで、患者が迷わず情報を見つけられるようになります。
患者がホームページに訪れた際、求めている情報に素早くたどり着けるかどうかは、ホームページを制作するうえで大切な視点です。たとえば、診療時間や診療科目、クリニックの所在地などの基本的な情報は、トップページや目立つ位置に配置する必要があります。こうした情報が見つけやすいだけで、患者の安心感や信頼感が格段に向上します。また、ホームページ内の各ページにメニューボタンなどを設けることで、患者が迷わず情報を見つけられるようになります。
最近ではスマートフォンからのアクセスが大半を占めているため、自院のホームページがスマホに対応していない場合は、レスポンシブデザイン※への切り替えなど早急な対策が必要です。
※レスポンシブデザイン
画面サイズに応じてレイアウトが調整され、パソコン・スマートフォン・タブレットなど各種端末で快適にホームページが閲覧できる仕組み
SEO対策
SEOとは何か?
SEO(Search Engine Optimization)は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索した際、クリニックのホームページを検索結果の上位に表示させるための一連の施策です。患者が「〇〇市 内科」「〇〇駅近く 耳鼻科」などのキーワードで検索したときに、自院のホームページが上位にヒットすれば、新規患者の獲得の可能性が高まります。
キーワード選定の重要性
効果的なSEOには、患者が検索しそうな「キーワード」を適切に選ぶことが重要です。たとえば、次のようなキーワードが挙げられます。
地域名+診療科目(例:「〇〇市 内科」「〇〇区 小児科」)
症状+診療科目(例:「喉の痛み 内科」「花粉症 耳鼻科」)
これらのキーワードを考える際には、患者の視点に立つことがポイントです。どのような言葉で検索されるかを想像し、それをホームページのタイトルや記事の中に自然な形で盛り込みましょう。
スマートフォン対応
Googleはモバイルサイトを基準にしてホームページを評価する仕組みを採用しています。スマートフォンなどのモバイル端末向けのホームページを中心に検索順位がつけられるため、SEO対策の観点からもホームページのスマホ対応(モバイル対応)は必須です。
相互リンクとSEO
他のホームページと互いにリンクをはり合うことを相互リンクといいます。相互リンクはSEO対策のひとつといわれますが、注意すべきは「リンク数が多ければいいというものではない」ということです。関連性の乏しいホームページとの相互リンクは、患者を混乱させるばかりか、低品質なリンクとして検索エンジンからの評価を下げる可能性もあります。一方で、連携医療機関や公的機関のホームページなど、患者の利便性・有益性を高めるためのリンクは、ホームページの信頼性を高めるために有効です。
SEO対策は、効果を実感できるまで数か月かかることも珍しくなく、長い目で取り組むべき施策です。SEO対策を施したホームページを運用し、検索エンジンの評価が上がれば、長期的に新規患者を集め続けることが可能となります。
オフライン対策
ここまでホームページを活用した集患対策を紹介してきましたが、集患対策のなかにはオフラインで実行できるものもあります。オンライン上のすべての人をターゲットにしたオンライン対策とは異なり、オフライン対策は主に近隣住民に向けた施策です。
看板・街頭広告の設置
看板や街頭広告の設置は、地域住民はもちろん、通勤・通学で近隣エリアを訪れる人にも、自院を知ってもらうために有効な手段です。いざ受診が必要になったとき、看板を目にした人に思い出してもらえるよう、デザインや設置場所を検討しましょう。
看板等の設置には法律や条例等で定められたルールがあるため、広告代理店などに相談することをおすすめします。
雑誌・新聞・チラシへの広告掲載
地域のフリーペーパーや新聞などに広告を掲載する、またはチラシを配布するなどして、自院の存在と特長を広めましょう。広告媒体はターゲットとなる患者層の目に触れやすいものを選びましょう。
院内でできる対策(接遇や待ち時間の改善)
クリニックの評判を上げる取り組みも、集患対策には重要です。患者満足度調査などを実施し、接遇や待ち時間といった自院の状況を客観的に把握し改善を図ることは、患者満足度の向上につながり、リピーターや口コミによる紹介の増加も期待できます。
オフライン対策は近隣住民に対してより直接的にアプローチする施策です。看板の設置や広告の原稿制作・印刷など、費用と時間がかかるものもありますが、オンライン対策と合わせて検討してみてはいかがでしょう。
オンラインでもオフラインでも守るべき「医療広告ガイドライン」
オンラインでもオフラインでも、医療機関が広告を出す際は「医療広告ガイドライン」を守らなければなりません。広告できる内容や表現方法など、必ず確認しておきましょう。
【参考資料】
厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)令和6年9月13日最終改正」
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」
ホームページは集患対策のメインツール
クリニックの集患対策にはさまざまな方法があります。
なかでもホームページの見直しは、比較的手軽に始められる施策です。認知度向上や競合との差別化、患者との信頼関係の構築など、多くのメリットがあります。
これから集患対策をお考えの方は、この記事で紹介したポイントを参考に、自院に最適な集患対策を検討・実践してみてください。
ニチイ学館の医療機関・調剤薬局向けホームページ制作サービスMediClips(メディクリップス)は、レスポンシブデザインでスマートフォンにも対応。
クリニックのホームページ制作・リニューアルでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
初期費用0円・月額(税別)4,800円~ MediClips(メディクリップス)サービス詳細ページはこちら▶